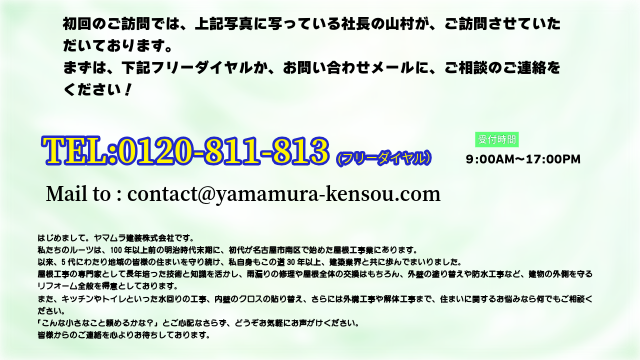名古屋市南区【屋根葺き直し】屋根沈下による雨漏り修理!瓦と土を撤去し原因の腐食板を特定!瓦の再利用と屋根養生と安全管理
writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔
名古屋市南区で屋根沈下の雨漏り修理!瓦再利用の葺き直しと土撤去で腐食原因を解消
「大雨の時だけ雨漏りする」という名古屋市南区のお住まい。
屋根が沈下していた原因を突き止めるため、いよいよ本格的な工事が始まりました。
今回は、使える瓦を丁寧に外して再利用する「葺き直し」の解体作業をレポート。
大量の重い土との格闘や、雨漏りを引き起こしていた腐食した木材の正体など、普段は見られない屋根の内側を詳しくご紹介します。
前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓
『名古屋市南区【雨漏り修理】足場設置の裏側!敷地内でも道路占用許可を取得する理由とは?安全管理と法令順守を徹底』
初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓
『名古屋市南区【屋根現地調査】大雨で2階が雨漏り?原因は瓦の沈下と屋根下地の腐食!狭小地でも安心3割だけの部分補修』
雨漏りの原因は屋根の沈下?瓦と土を撤去して葺き直し工事をスタート

先日よりご紹介している名古屋市南区の現場レポートです。
こちらの2階建て切妻屋根のお住まいでは、屋根の右側部分が目に見えて沈下しており、そこにできた隙間から大雨の時だけ激しい雨漏りが発生していました。
前回のブログでは安全確保のための足場設置の様子をお伝えしましたが、いよいよ今回から本格的な修繕作業へと入ります。
事前のお見積りと打ち合わせで決定した通り、屋根全体をやり直すのではなく、損傷が激しい約30%の範囲に限定した「葺き直し工事」を進めていきます。
まずは、既存の屋根瓦を一枚ずつ丁寧に取り外し、その下にある大量の屋根土を撤去する解体作業からスタートしました。
昔ながらの工法で建てられた屋根には、瓦の固定や断熱のために多くの土が使われていますが、長年の雨漏りで土が流出したり、逆に水分を含んで重くなりすぎたりすることが、今回のような屋根沈下の原因となるケースが多々あります。
瓦と土をすべて取り除くことで、屋根を一度骨組みの状態に戻し、沈下の根本原因となっている下地の腐食具合をあらわにします。
ホコリの舞う大変な作業ですが、ここを丁寧に処理することが雨漏りを完全に止めるための第一歩ですので、熟練の職人が手際よく作業を進めてまいりました。
目次
窓ガラスを守る!プロが実践する「養生シート」のひと工夫

いよいよ屋根の上での解体作業が始まりますが、その前に決して欠かせない重要な工程があります。
それは、既存の建物を傷つけないための徹底した「養生(ようじょう)」です。
屋根瓦や土を撤去する際、万が一手が滑って破片が落下してしまうと、その真下にある1階の窓ガラスや外壁を直撃してしまう恐れがあります。
そのような事故を未然に防ぐため、作業エリアの直下にあたる窓周辺には、厚手のブルーシートを隙間なく張り巡らせて保護を行います。
ここで単にシートを貼るだけではないのが、私たち専門業者のこだわりです。
シートを貼る際は、ただ窓を覆うのではなく、建物から離れた「足場の鉄骨部材」の方へ向かってピンと引っ張るように固定していきます。
こうすることで、建物側から足場側へ向かってシートに斜めの傾斜が生まれます。
仮に屋根から瓦の破片などが落ちてきても、このシートの斜面がクッションとなって受け止め、建物とは反対側の足場の方へと滑り落ちる仕組みになっているのです。
大切なお客様のお住まいをお預かりする以上、工事とは直接関係のない箇所であっても、傷一つ付けないよう細心の注意と工夫を凝らして作業環境を整えています。
「葺き替え」と「葺き直し」は何が違う?既存の瓦を再利用する賢い選択

今回の屋根リフォームでは、お客様とご相談の上、「葺き直し(ふきなおし)」という工法を選択いたしました。
一般の方には少し聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、屋根の修理には大きく分けて2つの方法があります。
一つは、屋根の下地補強を行った後に新品の屋根材を載せる「葺き替え(ふきかえ)」。
そしてもう一つが、今回採用した、今ある瓦を一度取り外し、下地を綺麗に直した後に再度同じ瓦を元に戻す「葺き直し」です。
どちらも屋根の寿命を延ばすための重要な工事ですが、なぜ今回は新品に交換しなかったのでしょうか。
それには、今回の工事範囲が「部分的な修理」であるという点が大きく関係しています。
もし、修理する30%の部分だけにピカピカの新しい瓦を使ってしまうと、残りの70%の経年変化した瓦と色や質感が合わず、屋根全体のバランスがチグハグになってしまいます。
特に今回のような途中からの解体作業を伴う場合は、長年その家を守ってきた既存の瓦同士の噛み合わせや相性が最も良いため、あえて古い瓦を再利用する方が、機能面でも見た目の美しさでも理にかなっているのです。
このように、私たちは単に新しくするだけでなく、お住まいの状況や全体的な調和を考えた最適な工法をご提案しています。
瓦は捨てずに再利用!一枚ずつ手渡しで行う丁寧な解体作業

いよいよ本格的な屋根の解体作業が始まりました。
屋根職人が一枚ずつ丁寧に瓦をめくっていくのですが、今回は古い瓦を処分する「葺き替え」ではなく、既存の瓦をもう一度使う「葺き直し」工事であるため、その作業風景は非常に慎重です。
剥がした瓦は、職人同士がバケツリレーのように手渡しで受け取り、足場の最上段に特別に設置した作業床(ステージ)の上へと運んでいきます。
もしここで瓦を割ってしまったり、乱雑に扱って角を欠けさせてしまったりすれば、元に戻すことができなくなってしまいます。
そのため、単なる解体作業ではなく、大切な資材の「一時保管作業」という意識で進めています。
事前に屋根よりも高い位置に足場を組んで広いスペースを確保していたのは、実はこのように取り外した大量の瓦を、破損させることなく綺麗に並べて保管しておくためでもあったのです。
足場の上に整然と並べられた瓦は、再び屋根に戻る出番を待っています。
このように整理整頓を徹底することは、部材の破損を防ぐだけでなく、現場の安全確保にもつながります。
お客様の大切な資産を守りながら、確実な施工を続けてまいります。
カチカチに固まった土との格闘!瓦の下地を綺麗に取り除く解体作業


丁寧に瓦を取り外した後に現れたのは、長年にわたり瓦を支え続けてきた大量の「屋根土(葺き土)」です。
昔ながらの工法で建てられた屋根には、瓦の固定や断熱の役割を果たすために多くの土が使われていますが、数十年の時を経て、これらの土は湿気と乾燥を繰り返し、まるでコンクリートのようにカチカチに固まっていることがほとんどです。
手で崩そうとしても容易ではありませんが、ここでも職人の技が光ります。
金づちの先(釘抜き部分)を土の下に巧みに潜り込ませ、テコの原理を使ってグイッと持ち上げると、大きく固まったままの土がパカッと綺麗に剥がれる瞬間があります。
このように板チョコを割るように土を塊のまま撤去できると作業効率も上がりますが、その分、重量はずっしりと重くなります。
剥がした大量の土は用意しておいた土嚢(どのう)袋へと詰め込んでいくのですが、ここで欲張って袋いっぱいに詰め込むことはしません。
屋根の上という不安定な足場で、後ほどこれを地上へ降ろす作業が控えているため、職人が安全に持ち運べる重さに留めておくことが鉄則です。
屋根を軽くし、建物の負担を減らすための重要な工程ですので、手間を惜しまず、一つひとつ確実に袋詰めを行っていきました。
重い土嚢袋はどう運ぶ?専用昇降機が大活躍の搬出作業

屋根の上で袋詰めを終えた大量の土嚢袋は、足場の上の安全な場所に一度集約させます。
水分を含んでずっしりと重くなった土を、職人が一つひとつ抱えてハシゴを降りるのは非常に危険であり、効率も良くありません。
そこで登場するのが、私たち屋根専門業者の頼れる相棒である「エンジン付き荷揚げ機(昇降機)」です。
これはハシゴにレールと台車がついたような形状をしており、モーターの力で重い資材や廃材を自動で上げ下ろしできる専用の機械です。
職人同士が声を掛け合いながら、バケツリレーの要領で土嚢袋を機械の台車へと積み込み、操作を行いながら数袋ずつ慎重に地上へ送り出します。
下で待機しているスタッフがそれを受け取り、すぐさま運搬用のトラックの荷台へと積み込んでいきます。
あれほど屋根の上にあった大量の土が次々とトラックへ移され、荷台が山盛りになっていく様子を見ると、建物がいかに重い負担に耐えてきたかがよく分かります。
こうして全ての土を降ろし終え、適切に処分場へと運搬することで、屋根の上は驚くほどスッキリとした状態になりました。
不要な重量物がなくなり、これでようやく次の補修工程へと進む準備が整いました。
【雨漏りの爪痕】屋根が沈んだ原因はこれだ!腐食した化粧野地板の撤去作業


瓦と屋根土をすべて降ろし、ようやく屋根の骨組みがあらわになりました。
そこで私たちの目に飛び込んできたのは、雨漏りの恐ろしさを物語る光景でした。
屋根の軒先部分、下から見上げた時に見える「化粧野地板(けしょうのじいた)」と呼ばれる板が、雨水を含んで黒く変色し、ボロボロに腐食していたのです。
今回の雨漏りの発端は、屋根瓦が沈下して生じた隙間からの雨水の浸入でしたが、その水が長期間にわたってこの板を蝕み、強度を奪っていたことが改めて確認できました。
本来、屋根を支えるべき板がこのように腐ってしまえば、その上に載っている重い瓦や土を支えきれるはずがありません。
屋根の一部がぐにゃりと沈んで見えていたのは、まさにこの野地板が腐って重さに耐えられなくなっていたからでした。
ここまで劣化が進んでしまうと、表面的な補修で誤魔化すことは不可能です。
将来の安心のため、腐食が見られる範囲の化粧野地板はすべて撤去することにいたしました。
腐った木材を完全に取り除き、一度リセットすることで、ようやく新しい木材を受け入れる準備が整います。
悪い部分を残さず徹底的に直すことこそが、長持ちする屋根作りの基本です。
晴れ予報でも油断禁物!工事中の雨漏りを防ぐ徹底した「雨仕舞い」


本日の解体作業はここまでとなりますが、屋根を剥がした状態でそのまま現場を離れることは絶対にありません。
作業終了時間が迫る中、まずは剥き出しになった屋根部分に仮設の合板をビスで固定しました。
これは後ほど本格的な工事の際に取り外すものですが、不安定な足元を固め、この上から被せる保護シートをピンと綺麗に張るための土台として重要な役割を果たします。
実は今夜の天気予報は降水確率0%の「快晴」となっていたのですが、私たちはその予報を過信することはありません。
屋根工事において、最終的な防水紙(ルーフィング)を施工するまでは、お住まいは言わば「無防備」な状態です。
万が一、夜間に予期せぬ雨が降れば、即座に雨漏りにつながってしまいます。
そのため、晴れの予報であっても必ず厚手のブルーシートで屋根全体を覆い、雨水の浸入を完全に防ぐ「雨仕舞い(あまじまい)」を徹底して行いました。
工事中であってもお客様に安心して夜を過ごしていただくこと、それが私たちの守るべき最低限のルールです。
明日も万全の状態から作業を再開いたします。
次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓
『名古屋市南区【瓦施工前準備】厚さ12mmの野地板合板で雨漏りに強い頑丈な屋根下地補強!防水紙と桟木施工で軽量化!』