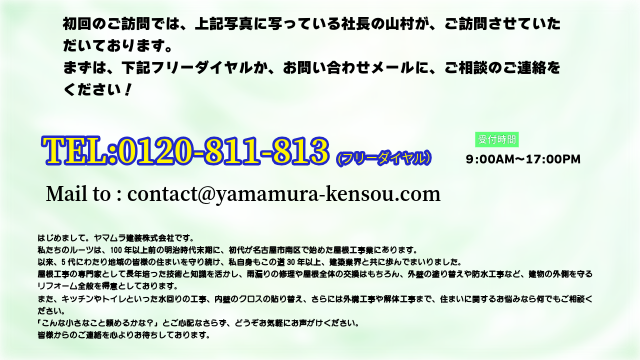名古屋市南区【屋根谷部修繕】谷樋のサビは雨漏り信号!瓦のズレや飛散も防ぐ台風・地震に強いビス固定工法まで解説!
writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔
【名古屋市南区の屋根修理実例】雨漏りを招く谷樋のサビ!放置の危険性と正しい修理法
ご自宅の屋根、最近じっくりと見たことはありますか?
屋根の面が合わさる「谷」の部分に、もし赤いサビを見つけたら要注意。
それは、雨漏りの一歩手前の危険なサインかもしれません。
放置すれば、いずれ谷樋に穴が開き、修理が大規模になることも。
この記事では、名古屋市南区で実際に行った谷樋の修理工事をもとに、その原因と正しい対処法、さらには台風や地震から家を守るための最新の屋根補強策まで、専門家が徹底解説します。

先日、名古屋市南区にお住まいのお客様より「屋根の谷部分が錆びているようだ」とのご相談を受け、点検と修理工事を行いました。
屋根には、雨水を集めてスムーズに地上へ流すための「谷樋(たにどい)」という重要なパーツがあります。
こちらのお宅では、谷樋にあまり屋根では使用されない材質の金属が使われており、長年の雨風の影響で経年劣化が進行していました。
その結果、塗装が剥がれ、腐食して真っ赤なサビが広がっている状態でした。
このまま放置すれば、いずれ谷樋に穴が開き、雨漏りの直接的な原因となってしまいます。
また、屋根瓦の飛散防止用に設置されていた古い鉄棒も、役目を終えてズレが生じていたため、安全性向上のために撤去いたしました。
今回の工事では、耐久性の高い新しい谷樋板金に交換し、雨漏りの心配を解消しました。
普段なかなか目の届かない場所ですが、谷樋の劣化は建物の寿命を縮める重大な問題につながります。
少しでも気になる点がございましたら、手遅れになる前に、ぜひ一度私たち専門家にご相談ください。
目次
屋根のプロが解説!雨漏りを防ぐ「谷樋交換」の丁寧な作業工程

まず、経年劣化で腐食してしまった古い谷樋を取り外す作業から始めます。
谷樋は屋根瓦の下に差し込まれる形で設置されているため、そのまま無理に引き抜くことはできません。
もし力任せに作業すれば、周りの大切な瓦を割ってしまったり、屋根の下地を傷つけたりする恐れがあります。
そこで私たちは、谷樋に重なってかぶさっている周辺の屋根瓦を、一枚一枚慎重に取り外していきます。
このひと手間を確実に行うことで、屋根全体への負担を防ぎ、安全に作業を進めることができるのです。
周辺の瓦をすべて撤去し、谷樋が完全に見える状態になってから、ようやく劣化した本体の取り外しを行います。
このように丁寧な下準備をすることが、雨漏りを確実に止める高品質な屋根修理につながります。
雨漏りを完全に防ぐ!新しい谷樋の設置と防水処理


まず、今後の腐食を防ぐために、屋根に適した耐久性の高い材質の谷樋を設置していきます。
そして、最も重要なポイントが、谷樋同士のつなぎ目の処理です。
この部分は雨漏りの原因になりやすいため、専用のコーキング材を使って隙間を完全に埋め、接着します。
これにより、豪雨の際に雨水が逆流したり、わずかな隙間から水が浸入したりするのを確実に防ぐ防水層を形成します。
防水処理を徹底した後、工事の最初に丁寧に取り外しておいた屋根瓦を、一枚一枚元の場所へ戻していきます。
屋根土でしっかりと固定しながら葺き直し、瓦がズレたりガタついたりすることのないよう、美しく頑丈な屋根に復旧させて作業は完了です。

谷樋交換工事もいよいよ最後の仕上げとなります。
この最終工程は、屋根全体の強度を高め、将来の安心を守るための非常に重要な作業です。
元の位置に葺き直した屋根瓦ですが、より強固に固定するために、瓦の接合部などを耐候性の高い専用のコーキング材で補強していきます。
この作業の目的は、瓦一枚一枚の結束力を高め、ズレや浮き上がりを防止することです。
これにより、近年の大型台風による強風で瓦が飛ばされたり、地震の大きな揺れで瓦がズレたり落下したりするリスクを大幅に軽減できます。
雨漏りを直すだけでなく、万が一の自然災害に備える「防災」の観点からも極めて効果的な施工です。
ご自宅の屋根は大丈夫?古い瓦屋根に見られる”鉄の棒”の正体と役割

築30年以上経つ日本瓦の屋根で、屋根のフチに沿って鉄の棒が取り付けられているのをご覧になったことはありますか?
これは、主に1990年頃までよく採用されていた、昔ながらの台風対策のひとつです。
では、なぜこのような鉄棒が取り付けられていたのでしょうか。
屋根の先端部分である「軒先」や、側面にあたる「ケラバ」の瓦は、構造上、屋根から少しはみ出しています。
そのため、台風のような強い風が下から吹き上げた際に、瓦が煽られて飛ばされやすい弱点がありました。
そこで昔の職人さんたちは、この風に弱い部分の瓦を、皮膜で覆われた一本の鉄棒で繋ぎ合わせるという工夫を凝らしました。
万が一、一枚の瓦が風で持ち上げられそうになっても、連結された他の瓦全体の重さで抵抗し、飛散を防ごうという考え方です。
これは当時の職人さんたちの知恵が詰まった工法と言えるでしょう。
ただし、現在ではこの鉄棒自体が経年劣化で錆び、屋根を傷める原因になることもあります。
【要注意】古い屋根の鉄棒、サビていませんか?放置が危険な理由と最新の瓦固定法


かつて瓦の飛散防止として有効だった屋根の鉄棒ですが、設置から数十年が経過した今、経年劣化により、かえって屋根の安全を脅かす存在になっている場合があります。
劣化の主な原因は、鉄棒を瓦に固定している「針金」です。
針金が長年の風雨で伸びて緩むだけでなく、より深刻なのがサビの連鎖です。針金が錆びると、そのサビが鉄棒を覆う皮膜を破ってしまいます。
すると、剥き出しになった鉄棒本体も内部から錆び始め、膨張して固定していた針金を自ら切断してしまうのです。
こうなると飛散防止の役目を果たさないばかりか、ズレた鉄棒が屋根を傷つける原因にもなりかねません。
そこで現在の屋根修理では、まず役目を終えた古い鉄棒を安全に撤去します。
その後、瓦の一枚一枚に専用の工具で丁寧に穴を開け、防水性の高いパッキンが付いたビスで屋根の下地に直接、強固に固定します。
この方法なら、瓦を一点ずつ確実に保持できるため、台風や地震に対しても非常に高い強度を発揮します。
古いお住まいでも、適切な方法で補強すればまだまだ安心です。
【工事完了報告】瓦のビス固定で屋根がスッキリ!プロの最終清掃までお任せください


一連の工程を経て、屋根の修理工事が無事に完了いたしました。
今回は、美しく生まれ変わった屋根の様子と、私たちのこだわりの一つでもある最終清掃についてご報告します。
こちらが、防水パッキン付きの専用ビスで瓦を一枚一枚しっかりと固定した後の様子です。
これで、台風や地震の揺れに対しても安心の強度を確保できました。
また、以前は屋根の端にあった古い鉄棒を撤去したことで、見た目も非常にスッキリとし、美しい仕上がりにお客様からも大変お喜びの声をいただいております。
そして、屋根の上の全ての作業が完了したら、資材や道具を慎重に下ろし、最終清掃に入ります。
業務用のブロワー(送風機)を使い、作業中に出た瓦の細かなクズやホコリなどを隅々まで徹底的に吹き飛ばします。
お客様の大切なお住まいだからこそ、工事前よりもきれいな状態でお引き渡しすることが私たちの信条です。
見えない屋根の上の清掃まで、最後まで責任をもって丁寧に行いますので、安心してお任せください。
初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓
『【屋根谷部修繕】名古屋市南区 雨漏り寸前の谷樋交換!瓦は再利用で費用削減!危険な鉄棒を撤去し台風に備える飛散防止工事』
ヤマムラ建装 株式会社では